森ビル 杉山央氏×未来の街【後編】 アフターコロナの街における、コミュニティ・公共空間とモビリティの可能性
未来の都市・街づくりをテーマに、森ビル株式会社の杉山央氏とFPRC研究員の藤元、早川(プロフィールはこちら)が対談を行った。森ビルは「東京を世界一の都市」にすることを目指し、2023年に竣工予定の虎ノ門・麻布台プロジェクトをはじめ、数十年の歳月をかけて大規模都市再生事業に取り組んでいる。新しくできる「街」においては何が価値となるのだろうか。
前編に続く後編では、コロナ流行は大量生産を基準とした「工業化社会」モデルの終焉に気づくきっかけになるのではないか、という藤元の仮説から議論が始まった。
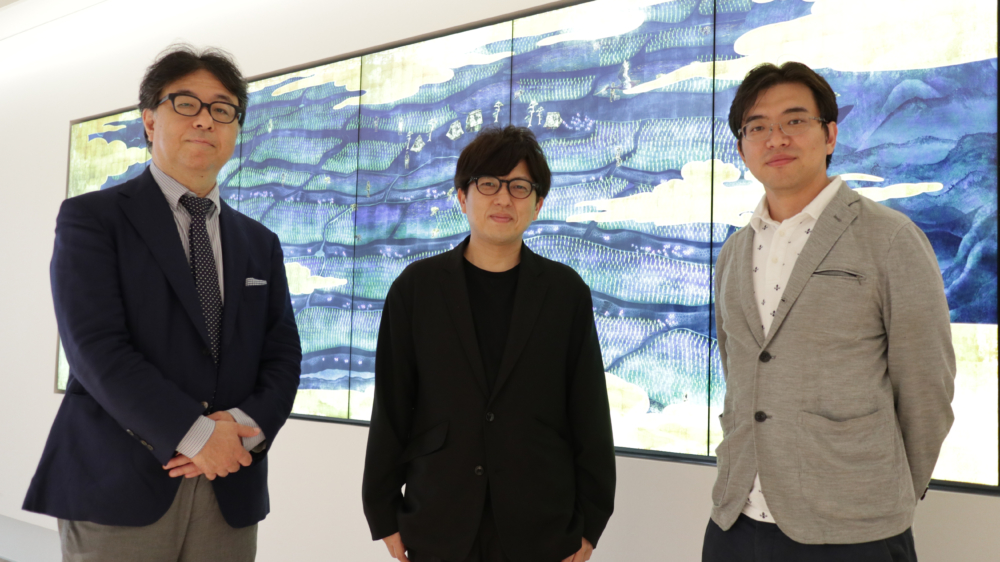
(左から:藤元、杉山氏、早川)
コロナ後の街:コンパクトシティとコミュニティ
藤元:
都市の歴史を考えると、農地解放で農民が都市に流入して工場で朝から晩まで働いて、という工業化社会のモデルが都市を急速に発展させてきた経緯があります。そこから、数十年前に工場が都会になくてもいいことがわかり、工場は郊外に移転しています。気がつくといつの間にか知的労働が都会に残されて、今回コロナで知的労働は会社に行かなくてもできる、ということがわかってしまったんですよね。どうして私たちは通勤していたんだろうと。
そう考えると、工業化社会はもう終わって次のフェーズに入っているのに、都市においては工業化社会のモデルを引きずっていた部分が多かったということに気づくきっかけとして、コロナは大きなインパクトがあったのかなと思っています。今後、都市で生活するとはどういうことかという点がますます問われるようになり、東京と香港は何が違うのかなど、都市同士の魅力を比べる競争の時代に入る気がしています。森ビルさんは東京を世界で一番魅力的な都市にすることに取り組んでいらっしゃいますが、これからの時代の都市について、ご意見はありますか。
杉山:
豊かな都市の理想は、コンパクトシティだと思っています。森ビルは、住宅と働く場所と遊ぶ場所、買い物する場所など、いろいろな機能がすべて徒歩圏内にあるような街づくりをしています。コロナが流行したことで、近所の公園がパブリックスペースとしてすごくにぎわっていたり、近所の商店街がにぎわっていたりして、徒歩圏内の幸せみたいなものをすごく感じました。これからの生活様式にとってすごくいいヒントをみんなが体験したのではないかと思います。
コロナをきっかけに無駄な移動がだんだんなくなってくると、住む場所の徒歩圏内に働く場所、遊ぶ場所、そしてコミュニケーションや共創の場があるコンパクトシティの利点が際立ってきます。人には、自分一人だけで何かをするだけでなく、ほかの人と一緒にアイディアを形にする共創のようなものが必要だと思います。都市におけるデジタルとリアルの関係性の話で言ったように、都市をコミュニケーションする場として捉えると、コンパクトシティの中でいろいろな人が混じり、交流して楽しみながら生活するという街づくりが良いんじゃないかと改めて感じています。
早川:
さきほど杉山さんがおっしゃったように、私もパブリックスペースの価値が再認識されていると思っています。今まではディベロッパーの立場からすると、パブリックスペースは非収益部門じゃないですか。そういうところにはあまり積極的な投資をしないというこれまでの価値観が、コロナをきっかけに変わって、パブリックスペースの豊かさが価値になるという方向性になるんでしょうか。

杉山:
そうですね。一般的な開発では、ビルを建てて余ったところを緑地にするのですが、2023年に竣工予定の虎ノ門・麻布台プロジェクトでは、考え方自体を逆にしています。最初に広場をどこに取るかを考えてプランニングしているんです。緑化など、人々にとっての憩いの場があること自体が街の価値になって、街のブランディングに寄与するんじゃないかという想定でいます。
藤元:
コロナで工業化社会が終焉を迎え、中世以前に重視されていた価値が取り戻されると考えると、街もやはり中世のように、広場や教会などコミュニティの拠点が街の中心になると思います。今までの工業化社会では、効率だけを考えて街を設計していたのが、街って人が幸せになるためのものだよね、ということが取り戻されて、人が中心の設計になるのかなと思っています。
杉山:
コミュニティは、私も重要だと思っています。これまでは、不動産は立地やスペックなどで評価されていて、例えばとある地域のAクラスビルの家賃はいくら、と相場が決まっていましたけれど、これからはそこにどういうコミュニティがあってどういう人々がいるかということが価値になってくる時代だと思います。そのコミュニティ形成をどうしていくかが、街の価値や人々が集まる幸せの指標になるんじゃないかと思っています。
人中心の街の設計と、モビリティ
藤元:
MaaSなどを考えても、今までは街の道路は車中心に設計されていましたが、パブリックスペースや、人が歩いていくことをベースに考える道路の設計が盛り上がっていますよね。
早川:
徒歩圏内の小さな移動への対応など、道路の考え方も変わってきているのでしょうか。
杉山:
歩車分離は街の魅力アップになると思うので、大規模再開発の時にはなるべく歩車分離の構造を作っています。歩車分離になった時に、都市型モビリティが歩道の方を走れるのかといったことを考える必要がありますね。
さきほど、お台場のデジタルアート ミュージアムでは自分の物語を体験できるという話をしたと思うのですが、モビリティがすごく面白いなと思うのは、移動はまさに自分の物語なんですよね。単なる閲覧型で順番が決まって見せられるものではなく、自分で見る場所の順番を決められれば、それによって体験が変わっていくものだと思うので、それはコンテンツになると思っています。

マルチハビテーション時代の街:「六本木eレジデンシー」
早川:
六本木ヒルズの「仮想住民」のような仕組みをつくることはありえますか。例えば、エストニアでは、「eレジデンシー」という、電子居住制度がありますよね。私が今スマートシティ関連のお手伝いをしている石川県の加賀市でも、「e加賀市民」のようなもの作ろうかという話が出ています。六本木ヒルズでも、バーチャル世界の森ビルレジデンシーのようなものができそうだと感じます。
杉山:
面白いですね。サブスクモデルで会員制度を作るというのは、街としても非常に魅力を感じています。街の応援団ですよね。街のファンとのエンゲージメントが高まるので、そういう仕組みは研究していきたいです。
藤元:
将来マルチハビテーションが進むと、制度的には住民税の分割納入を実現してほしいと思っています。例えば、3か所に住んでいる人が住民税を3分割して納めることができれば、おそらく住民としてのアイデンティティも行使しやすいですよね。制度が簡単に変わらないのであれば、例えば住民税のようなものをサブスクモデルで住民が積極的に払って、遠隔に住んでいても何か価値として返ってくるようにする仕組みが考えられます。自分の愛着や便益を提供してほしい地域に対して積極的にお金を落としていくようなモデルは、これからマルチハビテーションの時代に増えていくような気がします。
杉山:
それが結果的にはコミュニティになるんでしょう。消費者の巻き込み方としては、ただ受け取るだけでなく作り手側に回ってもらうほうが、エンゲージメントが高まりますよね。お金を払っているんだけど自分が仕事をする側になるという、そういうやり方で街づくりや街の運営にコミットしていただくこともありかもしれないですね。
都市の本質・人間の本質は変わらない
藤元:
最後に、メッセージをお願いいたします。
杉山:
コロナによって社会や暮らし方が大きく変化して、「場の共有」から「時間の共有」の時代へと変化しています。その結果、東京で暮らすことの意味や、都市化に対する疑問について議論されるようにもなっています。DXで仕事環境の自由度が高まったことで、東京から地方に暮らしの拠点を移すことを提唱する意見もたくさん見受けられました。
私はそうした脱都市化の意見に対しては懐疑的です。世の中が変わっても、人間の本質、都市の本質は変わらないからです。人の数だけ理想の暮らし方が存在することは間違いないですが、心が動くような感動体験や、大切な家族や友人と一緒に喜んだり、おいしい食べ物を食べに行ったりといった、人間本来が持っている幸せを感じる行為は、デジタルで全て代替することは難しいのではないでしょうか。現状のテクノロジーではデジタルはまだ道具にすぎず、リアルな場でこそ、真に人間らしい豊かな生活を送ることができるのではないかと思います。
都市の素晴らしさは、様々な情報や人が集積することによって、そこから新しい人と人との交流が促進され、文化やカルチャーが芽生え、新しいビジネスやチャンスが生まれることです。そして、それは真に人間らしい楽しみ・喜びを生み出す舞台が都市であるということでもあります。人間の本質、都市の本質はこの先も決して変わることはないでしょう。
コロナ流行をきっかけに、パブリックスペースや徒歩圏内の豊かさの価値が再認識され、人を中心とした街の設計が戻ってくる。そして、この先も人が集まり交流する場であるという都市の本質は変わらず、コミュニティこそが街の価値となる。人を軸に街や都市を捉える視点は、未来の街を考えるうえで大きな示唆を与えているだろう。

