AIが変える教育の未来:中学生起業家と現役教師が描くAI時代の学び【第9回FPRCフォーラム】<第2部>

2025年6月、AI時代のビジネスと学びの変革を議論するイベント「AIが破壊する“成長戦略”」が開催された。
AI時代の到来によって、教育の根幹が問い直されている。従来の「教える」中心の教育から「学ぶ」主体の教育へ、受動的な学習者から能動的な探究者へ――AIがもたらすのは単なる効率化ではなく、教育そのもののパラダイムシフトだ。
この変革の最前線に立つのは、現役の中学生たちだ。中学生でAI教育分野で起業した近藤にこるさんは、「AI時代の教育を創る!」というビジョンを掲げ、同世代の「内側からの変革」を進めている。一方、筑波大学附属中学校の関谷教諭は、200人の評価を5分で完了させるAI活用から、幼稚園児に最新技術カードを見せる感性重視の授業まで、教育現場でのAI実践を積み重ねている。
真の教育DXとは何か。AIによる「個別最適化」の本質とは。そして、子どもたちが本当に必要としている学びの環境とは。本稿では、現役中学生、現場教師、そして教育プラットフォーム開発者による議論を通じて、AI時代の教育が目指すべき方向性を探る第2部の議論内容をレポートする。
第2部 教育×AI活用
中学3年生起業家が描く「AIと共創する学びの未来」

近藤 にこる
EdFusion代表
現在中学3年生の近藤にこるさんが、「AIと共創する学びの未来」をテーマにオンラインで講演を行った。2024年7月にAI教育分野でEdFusionを創業したにこるさんは、これまでの経緯と今後の構想について約15分間の講演を行った。

中学生が起業?きっかけは授業での「初めて知った」体験
にこるさんの起業のきっかけは中学1年生の総合学習で参加した起業家体験プログラムだった。「ここで私は初めて起業ということを知りました」と振り返るにこるさんは、学校の先生の後押しもあり、名古屋にあるスタートアップ支援拠点「STATION Ai」の学生起業家育成プログラム「STAPS」に参加した。同プログラムでは特別賞を受賞し、起業に対して「とにかく楽しい」「もっとやってみたい」という思いを抱くようになった。
さらに起業活動を広めるため、学校の部活動として起業部を立ち上げた。部活では仲間と社会課題を解決するアイデアを考えたり、AIを使った壁打ち会や5分ピッチなどを実施。様々な大会への出場も果たしている。
AIに触れた中学生が、なぜ教育を変えようと思ったのか
転機となったのは人脈を通じて参加した生成AIイベントでのモデレーター、出展体験だった。「この時はAIは名前しか知らない」状態だったにこるさんだが、初めて生成AIに触れ、シンギュラリティなどAIの進化を目の当たりにした。「AIに対する希望もありつつ、一方で私たち人間とAIの向き合い方を考える必要がある」と強く感じたという。
この経験を受けて「AI時代の教育を創る!」をビジョンに掲げ、2024年7月にEdFusionを創業した。創業後は精力的に活動を展開し、衆議院議員会館での講演や学校でのAI授業の実現、文化祭へのAI導入などを手がけた。今年の文化祭では自身が校内の生徒に向けてAI授業を行う予定だという。
これまでに20回以上の講演やワークショップを開催し、地元カフェでのAIスクール、高校や名古屋大学での講演、外国人向けワークショップなど幅広い層を対象に活動している。
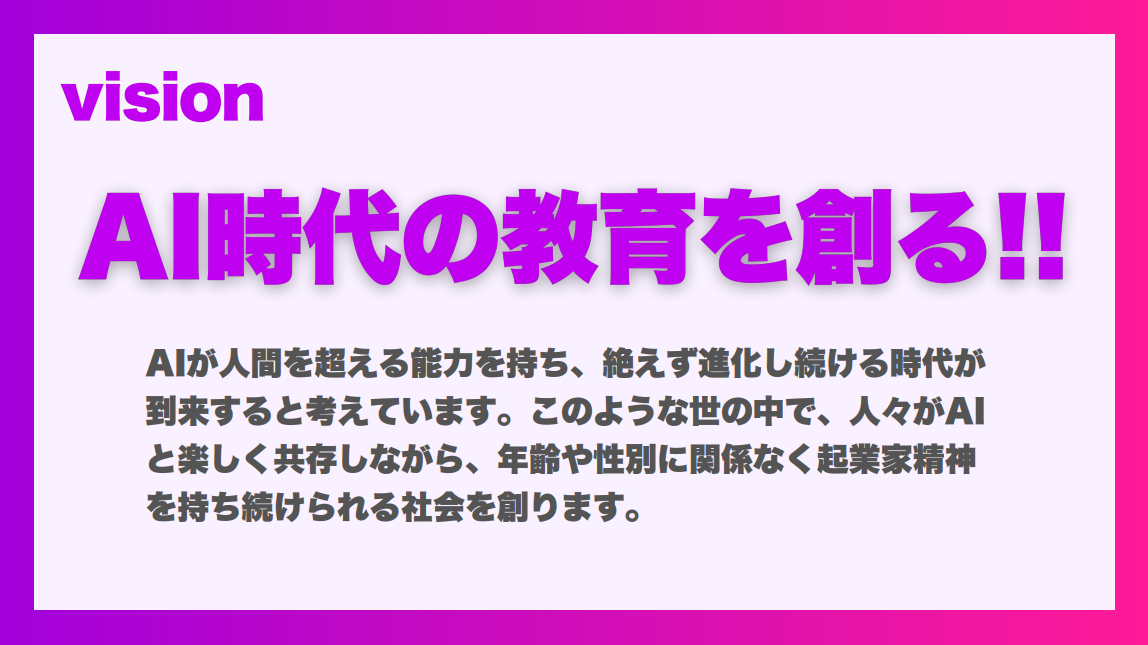
AI時代に子どもたちが身につけるべきスキルとは
にこるさんは次世代をターゲットに、AI時代に求められるスキルとして「AI活用法の教育」と「アントレプレナーシップ(起業家精神)」の2つを挙げる。AI活用法については「AIが進化するからこそ、まずはAIに触れていく教育が必要」とし、自身も英語学習やアイデアのブラッシュアップにAIを活用していることを紹介した。
アントレプレナーシップについては「AIが進化するからこそ、すべてやってもらうだけじゃなく、私たち人間が自らやっていく必要性がある」と説明。AIを「自分を表現する存在」と位置づけ、プレゼン資料の画像生成や趣味のクライミングと組み合わせた活用など、具体例を交えながらAIとの共存の在り方を示した。
子どもたちの「やりたい」気持ちと現実の機会には、大きなギャップがある
今後の活動として、「次世代の挑戦で循環する教育経済圏」の創出を目指している。能登半島地震時のアンケート結果を引用し、子どもたちの復興協力意欲(6割以上)に対して実際の機会(1割未満)という大きなギャップを指摘。「意欲と機会に大きなギャップがある」として、子どもたちが発信・挑戦できる環境の不足を課題として挙げた。
また、全国の子ども向け社会課題イベントの約3分の2が東京・大阪・愛知に集中し、小中学生対象は1割しかないという現状も示した。
「BUTTERFLY BASE」で変わる子どもたちの学び方
解決策として提案するのが「BUTTERFLY BASE」だ。リアル拠点とメタバースのデジタルツインを組み合わせ、誰でもどこでも環境にとらわれず挑戦できる場を提供する。構想の背景には、学校に行けなくなった身近な子がAIやプログラミングに触れることで自分の思いを形にできた体験があるという。

「バタフライ構想」の情報はこちら
https://ed-fusion.jp/butterfly-project
BUTTERFLY BASEでは、子どもたちがメタバース上でAIやプログラミングなどのスキルを習得し、それを活用して社会課題解決に取り組む。さらに学んだ子どもたちが教える側となる循環サイクルを構築する計画だ。「大人の皆さんに学んでいただくことで、子どもたちが笑顔で挑戦できる」三方よしのモデルを構想している。

BUTTERFLY BASEでの学習スペースのイメージ
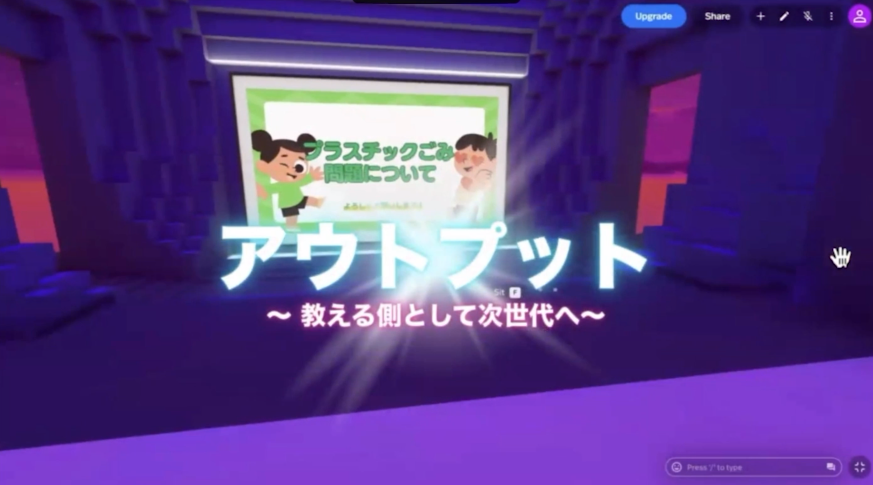
BUTTERFLY BASEでの子どもたちによるアウトプットのイメージ
明確なビジョンと豊富な実績を持つにこるさんの取り組みは、AI時代における教育の新たな可能性を示すものとして注目を集めている。
AIで教師の仕事と子どもの学びはどう変わる?教育現場でのAI実践事例
次に、筑波大学附属中学校の関谷教諭による教育現場でのAI活用事例が紹介された。関谷教諭は実践的な活用例を複数示した。

関谷 文宏
筑波大学附属中学校 教諭
200人の評価を5分で完了 AIが変える教師の仕事
最初に、200人の生徒の探究学習レポートをAIに分析させ、評価基準を4段階で設定して優秀者を抽出した事例を紹介した。AIが自動で評価基準(ルーブリック)を作成し、個別アドバイスまで生成するという。従来教師が膨大な時間をかけていた作業を一瞬で完了させることができる。
また、江戸時代と近代日本を図解する課題では、AIが生徒の手書き図を驚くほど正確に読み取った。文字の誤読があっても全体の文脈を理解し、意味の通る解釈を提示。図のない部分でも内容を推測して説明するなど、AIの理解力の高さが示された。
なぜ幼稚園生に「人工皮膚」を見せるのか?感性が学びの土台になる
関谷教諭が力を入れているのが、最新技術をカード化したツール(「未来コンセプトペディア」)を使って企業アイデアを創発する探求活動だ。幼稚園生から中学生まで幅広い年齢層を対象に実施し、幼稚園生は保護者とペアで参加する。参加者は人工皮膚やバイオプリンティングなど最新技術のカードを見て、「これ何?」「面白そう」という感想から入る。企業アイデアを作るワークでは、企業理念、使用する技術、その技術がもたらすメリットなどをワークシートに記入する。
関谷教諭は「驚く、感動する」といった感性が学習意欲の土台になると考えている。日本の教育は理性重視になりがちで、中学・高校に進むにつれて感情的な要素が軽視される傾向を問題視し、感性の部分を拡大する必要があると述べた。
関谷教諭の実践は、AIを単なる作業効率化ツールではなく、生徒の思考を深める教育パートナーとして活用する可能性を示した貴重な事例といえる。
ディスカッション:
中学生・教師・企業が議論する、AI時代の教育のあるべき姿とは?
プレゼンテーション後のディスカッションでは、現役中学生の近藤にこるさん、筑波大学附属中学校の関谷教諭、そしてプラスアルファコンサルティングの日野さんによる活発な意見交換が行われた。日野さんは4000社以上での採用実績を持つ同社で、学校内のデータを見える化し教育の質向上を支援するスクールマネジメントシステム「ヨリソル」の開発を手がけ、中学校から大学、塾予備校、教育委員会まで幅広い教育機関でのAI活用を支援している。

子どもたちはどのようにAIを活用しているか
現状、子どもたちはどのように生成AIを活用しているのか。にこるさんは具体的なAI活用例として、ノーコード開発ツール「Create.xyz」を紹介した。「このツールでは日本語の指示だけでウェブサイトを作成できる。子どもたちが自分のやりたいことをAIツールで表現できるのは非常に興味深い」と可能性を語った。
関谷教諭も「Google AI Studioでアプリを作成している。データを活用してプレゼン資料やインフォグラフィックを作成し、そのままアプリ化できる」として、生徒が教科書の内容をAIツールで再構成して発表する授業の可能性に言及した。
AIによる真の「個別最適化」とは?
また、関谷教諭は教師としての自身のAI活用事例について、「5分程度で200人分の評価データを作成でき、その精度も高い」と効果を実感していると語り、「このようなツールの導入が教育現場の変革につながる」とAI導入への期待を示した。
一方で現在の個別最適化について「決められた枠の中での最適化に留まっている。真の個別最適化とは、生徒自身が目標を設定し、それに合わせて学習内容を調整することだ」と述べ、生徒主導の目標設定の重要性を強調した。
中学生だからこそできる「内側からの変革」
起業部を立ち上げたにこるさんは、同世代への影響について振り返った。当初は参加者が2人という状況で廃部の危機もあったが、現在は防災課やAI推進課を設置した組織的な運営を実現している。
学校で得られる価値について問われると、「中学生という立場だからこそ内側から変えることができる。同じ目線だからこそ課題を共有できる」と答え、同世代だからこそ可能な変革の力を強調した。授業の意味についても「答えを導くまでのプロセスこそが重要。答えのないことを探求していくのが楽しい」と、探究学習の価値を実体験から語った。
生徒の声が届かない現実
ディスカッションでは、生徒の意見が学校運営に反映されない現実も明らかになった。にこるさんは代表者会での体験を例に挙げ、「生徒たちで話し合って決めたことが、翌日には職員会議の結果で覆される。それでは話し合いをした意味がない」と率直な感想を述べた。
この現状を受けて関谷教諭は、「生徒が自分の成長や意見をデータとして蓄積できる仕組みが必要だ。現在は原稿用紙に作文を書いてもデータとして残らない」と指摘し、生徒の声をデジタルデータとして蓄積する仕組みの必要性を提起した。
学校の「紙信仰」をどうやって変えるか デジタル化への段階的アプローチ
学校現場のデジタル化について、関谷教諭は「紙への信仰が根強く残っている。この状況からどう脱出するかが課題だ」と現場の実情を率直に語った。
これに対しにこるさんは「AIを授業に急に取り入れるのは難しいが、段階的に導入していくことが重要だ」として漸進的なアプローチの重要性を指摘。日野さんも「変革への意欲を持つ学校が、スクールマネジメントシステムを導入する傾向にある」と、学校側の変革意識が成功の鍵となることを確認した。
学校は「教える」ことばかりに夢中になってしまう
関谷教諭は現在の教育現場について、「学校は教師中心のティーチングエクスペリエンス(TX)になっている。教師が教えることに重点を置きすぎている」と分析し、「コーチングエクスペリエンス(CX)に転換すべきだ。教師はコーチングの役割を担うべきだ」として、教師の役割転換の必要性を提起した。
さらに生徒については「現在は受動的な学習者(スタディ)だが、能動的な探究者(エクスプローラー)になるべきだ」と述べた。
未来の教育への展望 「教える」から「学ぶ」へのパラダイムシフト
関谷教諭は教育の本質的な転換について興味深い提案を行った。「『教科書』ではなく『学科書』という表現にすれば、学習の主体が生徒自身であることが明確になる。『教科』は受動的なイメージがあるが、『学科』なら生徒が能動的に選択できる範囲が広がる」として、言葉の転換が意識変革につながるのではないかと述べた。
日野さんは教育の未来について「現在の子どもたちの世界は家庭と学校に閉じてしまっている」と現状を分析し、「AIを活用してより広い世界とのマッチングを実現し、コミュニティとの接続を図りたい」と提案した。
にこるさんは最後に「一人一人に合った教育の実現を目指している。小さなきっかけが大きな影響を及ぼすバタフライ効果のように、子どもたちが挑戦できる環境づくりを続けていきたい」として、機会創出への想いを語った。
おわりに
本フォーラムでは、なぜ「ビジネス」と「教育」という一見異なる領域を同時に取り上げたのか。その答えが、第1部から第2部へと橋渡しをしてくれた中学3年生起業家・近藤にこるさんの存在にある。
従来のビジネスの壁は既に破壊されている。 中学生であっても、やりたいことがあれば実現できる環境が整いつつある。一方で、そうした可能性を秘めた子どもたちが置かれている教育現場は、果たして彼らのような人材を本当に育てられているのだろうか。
今回のフォーラムを通じて見えてきたのは、日本中でワクワクしながら挑戦する子どもたちの姿だ。大人たちはついつい課題の話ばかりしてしまうが、実際には熱い思いを持った中学生・高校生が数多く生まれている。にこるさんは、その頂点の一人に過ぎない。
AIの真価は、そうした若い世代の「やりたい」という思いをエンパワーメントすることにある。 大人たちがまず考えがちな「自社の効率化」も確かに重要だが、AIを単なる効率化ツールとして捉えるだけでは、その可能性を見誤ってしまう。
AIが拓く新時代において、若い世代の情熱と創造性こそが、真の「超越最適」を実現する原動力となる。今回のフォーラムでの議論が、次のステップへのきっかけとなることを期待したい。
■ 登壇者プロフィール
近藤 にこる EdFusion代表
【自己紹介文】
現在、中学生3年生です。
私は起業に興味を持ってから、学校では部活動として「起業部」を設立し2024/07に「EdFusion」を創業しました。私は、「AI時代の教育を創る!」というビジョンを掲げ、AIと人間が楽しく共存する世界にするため挑戦し続けています!
関谷 文宏 筑波大学附属中学校 教諭
筑波大学附属中学校教諭。担当は社会科(歴史)。東京大学文学部国史学科卒業。東京都足立区の公立中学校で11年、東京都教育委員会指導主事として3年つとめた後、 平成17年に東京都を退職して母校に赴任し現在に至る。北方領土の返還を求める都民会議の教育者会議メンバーとして、生徒を引率して国後島訪問の経験あり。金融教育のモデル校、主権者教育の研究校としての実践あり。全国中学校生徒地域研究発表会(Fieldwork in Japan)の実行委員長をつとめる。経済産業省のSTEAMライブラリーのコンテンツへの作成協力(制作はブリタニカ・ジャパン)。ぜひ私の名前で動画検索して下さい。英語版でも学べます。
日野 貴之 株式会社プラスアルファ・コンサルティング HRソリューション本部 ヨリソル事業部 兼 生成AIイノベーション部 コンサルティング シニアプロフェッショナルマネージャー
大学卒業後、SEやSIerの経験を経て、2015年にプラスアルファ・コンサルティングへ参画。マーケティング業界にて定性情報の見える化やCRMに関する分析・施策立案を支援。
現在はヨリソル事業部にて教育業界におけるデータ一元化や校務効率化/データ利活用を推進。また、生成AIイノベーション部にも所属しており、教育業界における生成AIの活用にも力を入れている。
藤元 健太郎 D4DR 代表取締役 / FPRC 主席研究員
元野村総合研究所、元青山学院大学大学院 MBA 非常勤講師、関東学院大学非常勤講師。 1993 年からインターネットによる社会変革の調査研究、イノベーションに関わる多くのコンサルティング、スタートアップを支援。

